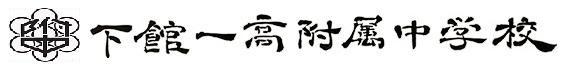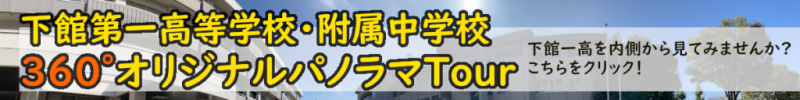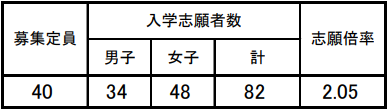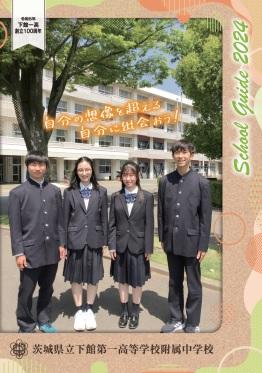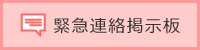入学予定者決定のお知らせ
令和6年度入学者選抜については、確約書提出が完了し、入学予定者が決定いたしました。
欠員補充は行いません。
令和6年度 入学者選抜志願者状況
志願者状況は以下の通りとなります。
※ 12/12(火)までに送信予定であった「受験票の準備ができた旨」の
メールは、12/18(月)までに送信いたします。
お知らせ
新着情報
学校説明会について
令和5年度の学校説明会の動画をアップいたしました。どうぞご覧ください。